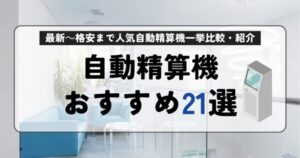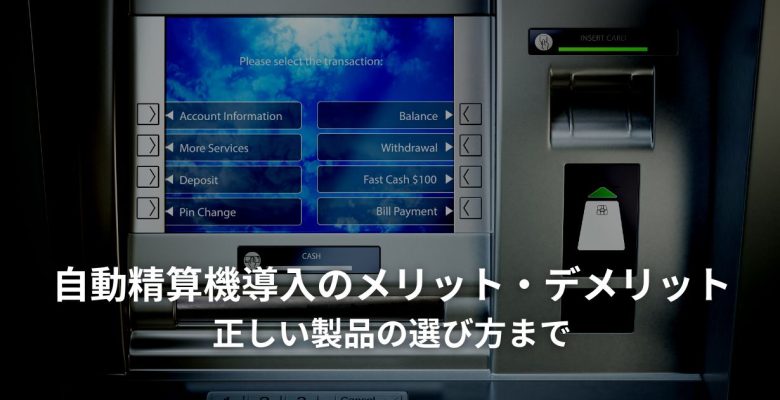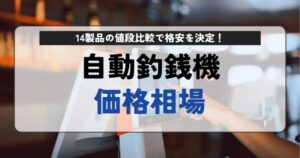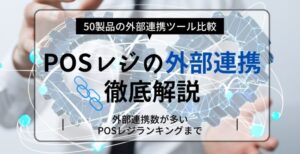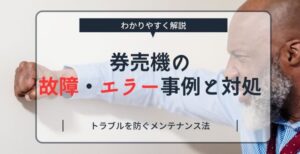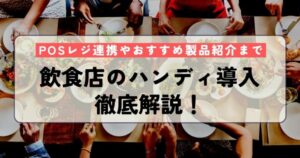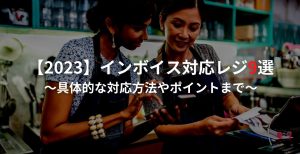近年、飲食店やホテルだけでなく、医療業界にも自動精算機の導入が進んでいます。
その背景にあるのが、新型コロナウイルスの感染拡大や慢性的な人手不足によるものです。自動精算機を導入することで、「衛生面の強化」や「業務効率化による人件費削減」などが期待されています。
しかし実際のところ、自施設で自動精算機の導入が本当に必要か迷っている方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、自動精算機導入のメリット・デメリット、選び方などを解説していきます。
本記事を読むと、自動精算機導入が自施設に適しているのかがわかり、正しい製品の選び方を知ることができるでしょう。
なぜ?自動精算機の導入が進む背景とは

冒頭でもお伝えしたように、現在、医療業界を中心に様々な業界で、自動精算機の導入が進んでいます。
その背景として考えられるのが、自動精算機の導入で下記の3点が解消されるからです。
・医療業界の慢性的な人材不足
・待ち時間が患者の最大のストレスになっている
・コロナウイルスの感染拡大
レジ精算を患者様自身で行うようになるため、スタッフとの接触を避けられ、新型コロナ感染拡大防止に繋がります。また、自動精算機の導入により、精算業務を行うスタッフの人員を減らすことができるのも理由の一つでしょう。
さらに、会計までの待ち時間なども短縮されることもあり、多くの業界で自動精算機の導入が進んでいます。
自動精算機導入のメリット
自動精算機を導入することで、どのようなメリットがあるのでしょうか。ここでは、下記の8つのメリットについて解説していきます。

それぞれ詳しく解説していきます。
会計スピードアップによる待ち時間の軽減
病院やクリニックにおいて、患者様の最大のストレスになっているものは、「待ち時間」です。厚生労働省が発表している「令和2(2020)年受療行動調査(確定数)の概況」によると、外来患者の待ち時間は
- 「15分未満」が28.0%と最も多い
- 「15分~ 30 分未満」が25.7%
- 「30分~1時間未満」が20.9%
となっており、1時間未満の待ち時間の割合が約7割となっています。裏を返せば、約3割もの方が1時間以上の待ち時間を過ごした経験があるということです。自動精算機の導入により、会計時の混雑を解消することができ、患者様の待ち時間軽減に繋がるでしょう。
出典:厚生労働省「令和2(2020)年受療行動調査(確定数)の概況」
業務効率化による人件費削減
自動精算機の導入で、会計業務の効率化による人件費削減が期待できます。これまでスタッフが行っていた精算業務を、患者様自身で行ってもらうことになり、そこにかかっていた人件費の削減が可能です。
また、人件費の削減だけでなく、スタッフが精算業務に充てていた時間を他の業務に使えるようになるでしょう。
会計ミスの防止によるスタッフ負担の軽減
自動精算機の導入により、会計ミスを防ぐことも可能です。現金の受け渡しやつり銭の計算は人間が行う以上、必ずミスが起こります。会計のミスは患者様からのクレームに繋がり、スタッフの心理的負担も大きいです。最悪の場合、スタッフの離職に繋がるケースもあるでしょう。
自動精算機にはそのような会計ミスが発生することがなく、心理的負担軽減による定着率アップにも期待ができます。
また、「自動精算機を導入している施設」というアピールにもなり、求人広告に記載することで応募率の増加も期待できるでしょう。
衛生面を強化できる
自動精算機を導入している施設は、お金の直接の手渡しがなくなり、必要最低限のやり取りで会計を済ませることができるため、接触機会が減ることによる衛生面の強化になります。新型コロナウイルスの影響で、店舗や施設の衛生管理に対する意識がより一層強まりました。
それは患者様側にも当てはまり、衛生面をしっかり行えていない医療施設は避けるようになる方も一定数いらっしゃいます。
衛生面をさらに強化し感染対策を強化したい医療施設にとっては、大きなメリットになるでしょう。
セキュリティの向上(盗難防止)
自動精算機の導入はセキュリティ向上にも効果が期待できます。従来のレジはキャッシュドロアーといい、簡単に開けられる仕様のものが多く、盗難リスクがありました。
実際に、レジのお金が盗難されるといったトラブルに悩まされている施設もあるでしょう。
自動精算機は簡単に開けられない仕様になっており、一部の管理者しか開けられないようにすることで盗難防止に繋がります。外部の人間による盗難だけでなくスタッフによる盗難も昨今多発していますが、そういったリスクを軽減することが可能になります。
スタッフのレジトレーニング時間がなくなる
自動精算機はそもそもスタッフがレジ業務を行うことがなくなるので、スタッフのレジトレーニングの時間を大幅に削減することが可能です。ただし使い方がわからない利用者のために最低限サポートができるだけのトレーニングは必要になります。
従来の会計業務と自動精算機の業務フローと比較すると、大幅に業務の簡略化が可能になります。
スタッフの負担も軽減され、ひいてはスタッフの定着率アップにも繋がるでしょう。
キャッシュレス決済導入がスムーズ
多くの自動精算機では現金のみならず、クレジットカードや電子マネーなどのキャッシュレス決済に対応しています。従来のレジでは、決済方式に対応した外付けの読み取り機器を導入する必要がありました。
さらに、有人レジで決済を利用する際は、患者様が決済方法を伝えてスタッフが決済時に端末に金額を手打ちするといった手間もあるでしょう。自動精算機はキャッシュレス決済の導入がスムーズで、患者様自身が決済方法を選び、決済を行うのでスムーズな会計が可能です。
新しい顧客体験の創出につながる
自動精算機は新しい顧客体験の創出に繋がります。
特に子どもが自動精算機の仕組みを楽しんで利用するといったことがあります。
これまでスタッフが行っていた精算業務を、自身で行える新しい体験が楽しいという理由で喜ぶ子どもも多いです。
他施設で自動精算機が導入されていない場合は、注目されることになり、宣伝効果に繋がるメリットも期待できるでしょう。
自動精算機導入のデメリット
自動精算機には多くのメリットがある一方で、デメリットもあります。
下記のデメリットを理解した上で、自動精算機の導入を検討してみてください。

初期費用・ランニングコストが高い
自動精算機の導入デメリットは、初期費用・ランニングコストが高いことです。種類や機能によっても費用は異なりますが、自動精算機の価格相場は初期費用200〜450万円、年間保守費用10〜20万円の価格帯が多いです。
また、製品によっては月額利用料やオプションが必要になるため、さらに高額になります。自動精算機の導入で、人件費削減効果や人材定着効果など、自施設にとって費用対効果があるかを検討する必要があるでしょう。
自動精算機の価格について詳しくは下記の記事で解説しています。

そもそも自動精算機ではなく、セルフレジ導入も選択肢
高額な費用を支払ってまで自動精算機の導入に魅力を感じない場合は、セルフレジの導入も選択肢の一つです。
精算から金銭の授受までを患者様1人で完結できるのが自動精算機ですが、セルフレジ(フルセルフレジ)も同様に患者さん一人で会計を簡潔させることが可能です。セルフレジのメリットとして、ほぼ同様の運用が可能でありながら導入費用が100~150万円と大幅に抑えられている点です。
自動精算機とセルフレジの違いとしては、以下の写真の通り、自動精算機が自動釣銭機や外付けの筐体、モニター画面などい一体となっている機器であるのに対して、セルフレジはモニター画面(タブレット端末の場合が多い)と自動釣銭機を合わせたような機器になります。(厳密には、セルフレジという大きな概念に自動精算機が含まれる形になりますが、多くの場合でセルフレジ、自動精算機というと前述のような認識となります。)
自動精算機

セルフレジ(フルセルフレジ)

セルフレジの場合、電子カルテ・レセプトとデータ連携不可の製品がほとんどですが、バーコード連携はほとんどの製品で可能です。また、「スマレジ」の製品であればセルフレジとして電子カルテ・レセプトとデータ連携も可能です。
ただしセルフレジの場合、外国語対応ができない点、キャッシュレス決済などは別途外付けで導入必要となる点などデメリットもあるので経営判断を行いましょう。

広い設置スペースが必要
自動精算機は床に設置する自立タイプやカウンターに設置するタイプがあります。どちらもサイズは大きいので、施設に広い設置スペースが必要になるでしょう。
例えば、奥行250mm×幅360mmのFLEXCOM Payは、自立タイプのコンパクトな自動精算機として知られています。
導入前には、あらかじめ自施設に設置できるスペースを確認してから検討するようにしましょう。
小型の自動精算機については以下の記事で詳しく解説しています。気になる方はチェックしてみてください。

釣銭補充が大変
自動精算機はセキュリティに優れている分、従来のキャッシュドロアーに比べて開閉が大変です。多少の時間がかかるため、つり銭補充が手間に感じる方もいらっしゃるでしょう。
しかし、通常のスタッフでは開けられないため、スタッフによる盗難防止に繋がります。
利用客の一部にはサポートが必要
自動精算機は比較的新しい機器です。特に高齢の方が多い施設では、自動精算機の使い方に戸惑う方もいらっしゃるでしょう。そのため、操作で迷っている方がいれば、スタッフが一部サポートに入る必要があります。
高齢の方が多い施設の場合は、自動精算機の使い方がわかりやすく、モニターが大きい製品を選ぶとよいです。
自動精算機を導入するかどうかの判断基準
ここまで、自動精算機のメリット・デメリットについてお伝えしてきましたが、自施設に必要かどうか判断が難しい場合もあるでしょう。
施設に自動精算機を導入するべきかどうかの判断基準を解説していきます。
コスト面から判断
前章でも解説したように、自動精算機には高額な導入コストがかかります。しかし、自動精算機の導入により、
- 会計がスムーズになることでより多くの診察が行える
- 業務効率化による人件費削減
- レジ教育の時間がなくなる
- スタッフ定着率アップによる採用費の削減
など、コスト面でメリットがあるポイントも多いです。
これらのメリットと導入コストを比較して、長期的な視点でプラスが多いと判断すれば、導入するとよいでしょう。
客層(患者層)から判断
デメリット部分でもお伝えしたように、患者様が高齢の方であれば、操作に一部サポートが必要な場合もあります。患者様の年齢層が高齢の方でほとんどを占める場合は、自動精算機の導入はあまり適していないといえるでしょう。
そのため、市街地にある若い方も多く受診する医療機関には自動精算機導入は非常におすすめです。導入前には必ず患者様の年齢層を把握し、導入検討をするとよいでしょう。
自動精算機の選び方
自動精算機の導入が決定し、いざ製品を選ぼうとしてもどの製品を選べばよいか迷う方もいらっしゃるでしょう。
ここでは、、自動精算機を選ぶ際に見るべきポイントを下記の4つ解説します。
- 電子カルテ・レセプト連携の有無
- 設置タイプ・サイズをチェック
- キャッシュレス決済対応の有無
- お金の処理能力
電子カルテ・レセプト連携の有無は?
自動精算機で会計をする場合、電子カルテ・レセプトと連携して会計の情報を自動精算機に伝える必要があります。
そのため、自施設で利用している電子カルテ・レセプトに対応しているかのチェックは必要です。
また、連携方法には「データ連携」と「バーコード連携」があり、それぞれで運用方法が異なります。
バーコード連携の自動精算機は、入出金データを取得できますが、下記のデータは取得できません。
- どのスタッフがいつ、いくら請求したか
- お釣りの返金額
- どのような方法で決済されたか
- 保険証利用の有無
- 科目内容
バーコード連携では、これらの細かなデータは取得できないため注意が必要です。
設置タイプ・サイズをチェック
自動精算機は「床置き型(自立タイプ)」と「卓上型(カウンタータイプ)」があります。ある程度の設置スペースが必要になり、小さなクリニックでは設置が難しい場合が多いです。クリニックなど設置スペースを確保できない施設は、カウンターなどに設置する「卓上型」がおすすめです。
床置き型の中では、FLEXCOM PaやNOMOCa-Stand (ノモカスタンド) などが、コンパクトサイズとして知られています。
設置スペースの確認は、自動精算機を導入する前に必ずしておきましょう。

キャッシュレス決済対応の有無
自動精算機を導入する際は、キャッシュレス決済に対応しているかの有無も確認しておきたい項目です。患者様の年齢層が若いほど、キャッシュレス決済の利用率が高くなり、ニーズがあります。
現金を使用する機会が少ない患者様にとっては、キャッシュレス決済の対応で患者満足度にも影響があるでしょう。そのため、若い患者様が比較的多い施設では、キャッシュレス決済に対応している自動精算機を選ぶことをおすすめします。
お金の処理能力
自動精算機を選ぶ際は、お金の処理能力も見ておきましょう。お金の処理能力が低い場合、スタッフだけでなく患者様の満足度低下にも繋がってしまいます。
例えば、「まとめて紙幣や硬貨を入れて処理できるか」、「5,000円札に対応しているか」などです。価格が安いモデルになると5,000円札に対応していない場合もあるため、事前にチェックしておきましょう。
まとめ
今回は自動精算機のメリット・デメリットや、正しい製品選びのポイントについて解説してきました。新型コロナウイルスの感染拡大や慢性的な人手不足により、自動精算機の導入が進んでいます。
自動精算機の導入により、「衛生面の強化」や「業務効率化による人件費の削減」、「待ち時間の短縮」など様々なメリットを得られます。一方で、「導入コストがかかる」「設置スペースが必要」などのデメリットがあるのも事実です。
メリットとデメリットを熟考し、最終的に導入コストを回収できるか判断してから導入を進めていくとよいでしょう。
本記事を読んで具体的な製品についても見てみたくなったという方向けに、以下の記事でおすすめランキング形式で各メーカーの自動精算機を紹介しています。気になる方はぜひチェックしてみてください。