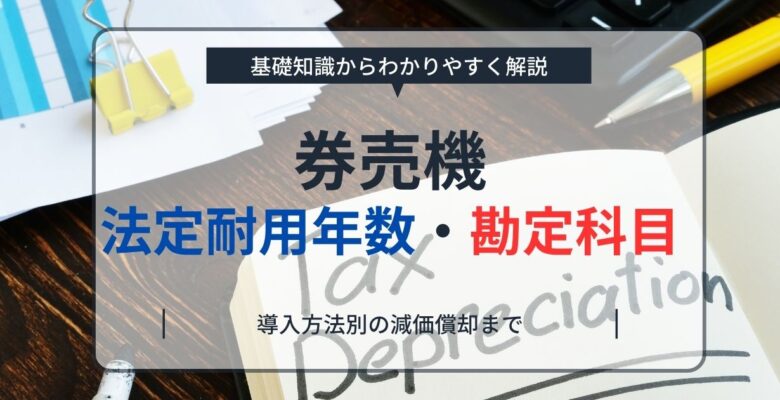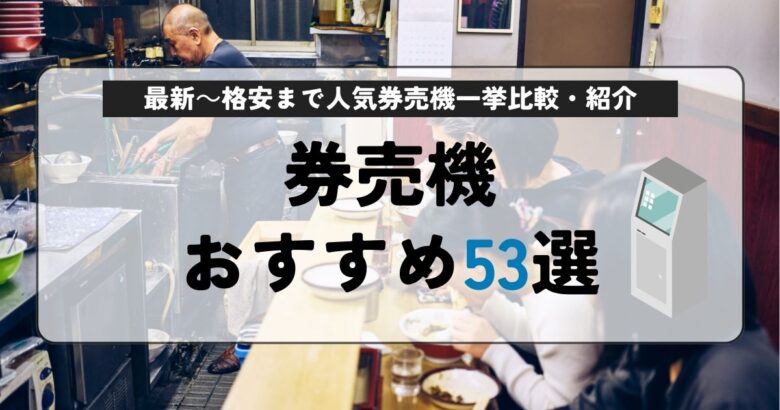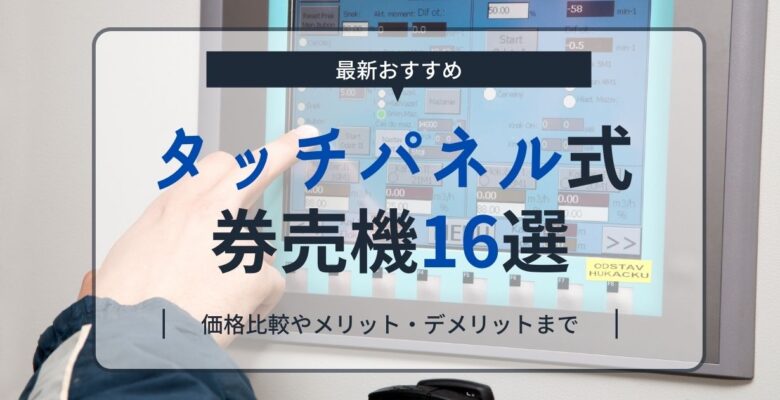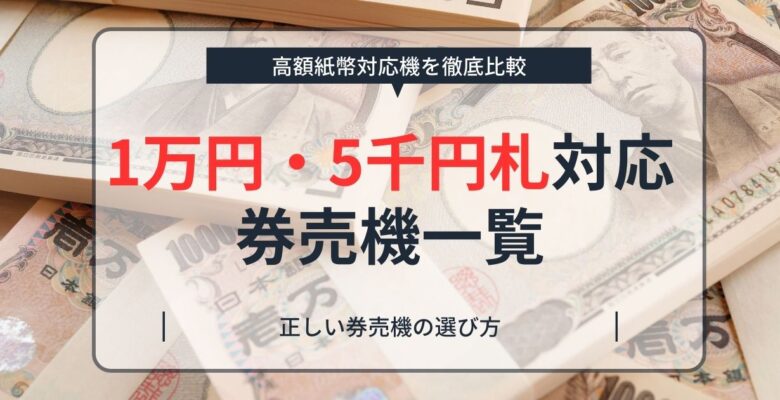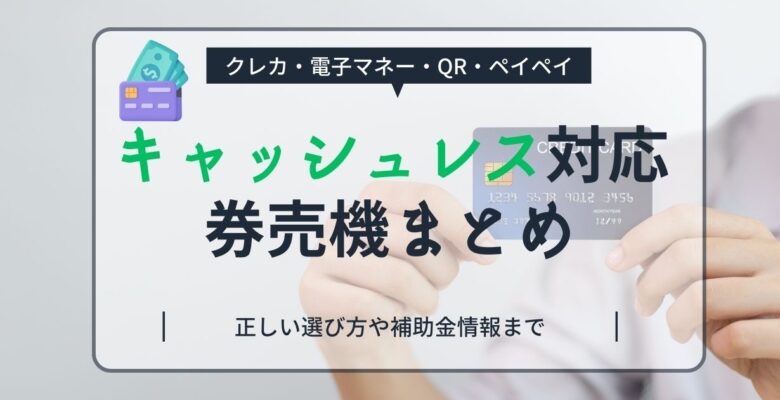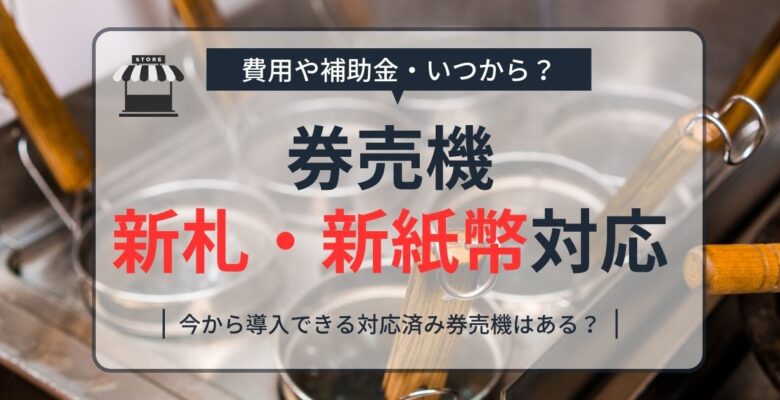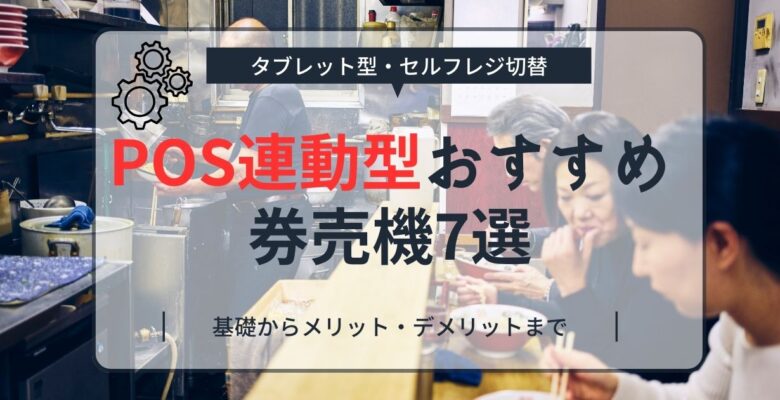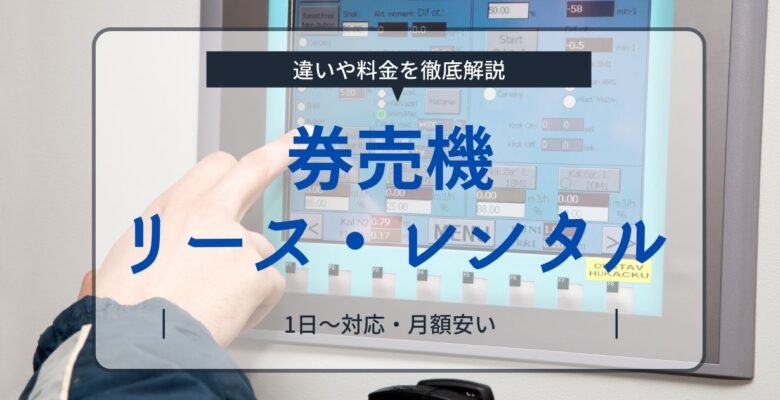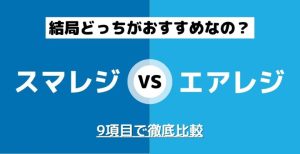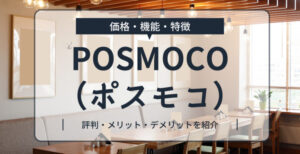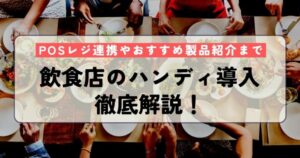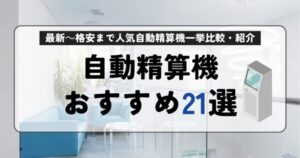券売機は、注文・会計業務の効率化や顧客満足度の向上につながる製品です。
導入にあたり、耐用年数や勘定科目、減価償却期間が気になる方も多いのではないでしょうか。
結論から申し上げると法定耐用年数は基本的に8年※と定められています。
※設置する業種によって異なる場合があります。詳しくは記事内で解説します。
また、物理的な耐久年数は使い方にもよりますが、法定耐用年数に比べて短く5~6年程度です。
その他、減価償却や勘定科目など、これから券売機の導入を検討している方は、会計処理や節税にも大きく関わってくる部分なので、
耐用年数については必ず確認しておくことが大切です。
本記事では、券売機の耐用年数や、導入時の節税テクニックなどを解説します。
券売機の法定耐用年数・減価償却期間は?
券売機の法定耐用年数は、基本的に8年※です。
ただし業種によって耐用年数は異なり、厳密には下記の通りです。
- 飲食店に設置する券売機の法定耐用年数:8年
- ホテルや旅館に設置する券売機の法定耐用年数:10年
- 飲食店・宿泊施設以外の場所に設置する券売機の法定耐用年数:5年
耐用年数は国税庁が、「耐用年数表」で機器ごとに定めています。
例えば飲食店なら項目としては、「機械・装置」の「飲食店業用設備」に含まれています。
購入の場合、一括で支払った費用が経費に計上されるわけではありません。
耐用年数の8年にわたって減価償却されていくので注意しましょう。
出典: 国税庁 確定申告作成コーナ よくある質問 耐用年数(機械・装置)
購入やリース、レンタルなど、導入方法によって耐用年数は違う
以下のように、券売機は導入方法によって耐用年数が異なります。
- 購入:基本的に8年
- レンタル:利用者は特になし
- リース(所有権移転):国税庁が定めた耐用年数(8年)
- リース(所有権移転外):リース契約をしている期間
耐用年数は、所有者の「資産」に対して定められる期間のことです。
そのため、券売機の所有権がレンタル会社にあるレンタルでは、利用者の資産ではないため、耐用年数について考える必要はありません。
リースの場合は、購入に準じた扱いとなり、利用者が減価償却の処理を行う必要があります。「所有権移転」の契約をしていれば、所有権は利用者に移るため、国税庁が定めた耐用年数(券売機は8年)に応じて減価償却を行わなければなりません。
ただし、「所有権移転外」契約のように、所有権がリース会社にある場合は、リース契約に基づいた耐用年数になります。リース契約の内容を確認して、耐用年数を把握しておきましょう。
券売機自体が故障せず安定して使える目安は5~6年
ここまで解説してきた券売機の法定耐用年数は8年です。
しかし、耐用年数は8年間で、故障せずに使える期間というわけではありません。
券売機自体の耐久力は5〜6年が目安といわれています。
もちろん、券売機の設置環境や使用頻度、メンテナンスの頻度などによっても異なります。
券売機を長く使い続けるためには、定期的なメンテナンスや清掃が欠かせません。
券売機が故障する原因で多いのは、紙幣・硬貨の詰まりです。
長く使用し続けていると、埃が溜まって詰まりやすくなるため、定期的に清掃を行うことで故障を避けられます。
故障の原因がわからない場合や、修理が必要な場合は、購入先に対応してもらいましょう。
券売機の勘定科目
勘定科目とは、会社の取引内容をわかりやすく分類する項目のことです。
券売機は細かい勘定科目に分類することができ下記の通りとなります。
- 飲食店に設置する券売機の勘定科目:飲食店業用設備
- ホテルや旅館に設置する券売機の勘定科目:宿泊業用設備※法定耐用年数も10年となります。
- 飲食店・宿泊施設以外の場所に設置する券売機の勘定科目:金銭登録機※法定耐用年数は5年となります。
券売機を設置する場所によっても異なるので、必ず知っておきましょう。
確定申告の際は、購入した券売機の総額を一括計上するのではなく、上記の基準に基づいて減価償却費として計上する必要があります。
耐用年数・減価償却ってそもそも何?|知っておきたい基礎知識を解説
「耐用年数や減価償却の意味をよく理解していない」
このような方も多いのではないでしょうか。以下の基礎知識は、節税をするときにも役立つので知っておきましょう。
- 法定耐用年数
- 固定資産
- 減価償却
- 勘定科目
ここでは、それぞれの言葉の意味を解説します。
法定耐用年数とは?
法定耐用年数とは、国が定めた固定資産を使える期間のことです。
資産の種類によって細かく定められており、その期間は「資産価値のあるもの」として経費計上ができます。
券売機の法定耐用年数は8年ですが、8年間使用できるという「耐久年数」と同義ではありません。
メンテナンスを怠れば3年で故障する場合もありますし、8年使えるケースもあります。「この期間は資産価値として維持できる」と国が定めたものなのです。
法定耐用年数を定めることで、消費者が機器の減価償却を平等に行えるようになります。
固定資産とは?
固定資産とは、長期にわたって利用するもの、もしくは1年以上使用される資産のことです。券売機は長期にわたって利用するものなので、「固定資産」になります。
固定資産の他に、「流動資産」や「繰延資産」があります。まず流動資産は、所有する資産のうち、短期間で現金化できる資産のことです。繰延資産は、会社経営の際に必要とした開業日や商品開発に関わる費用など、現金化できないものを指します。
そして固定資産は、土地や建物など、短期間で現金化できない資産のことです。券売機は固定資産とみなされるため、減価償却の処理が必要になります。
減価償却とは?
減価償却とは、固定資産の購入費用を分割して費用計上する会計処理のことです。券売機は長期にわたって利用する固定資産ですが、年数が経つにつれて劣化し、資産価値が下がります。
固定資産には「耐用年数」が定められており、その期間に少しずつ経費を計上することが可能です。基本的に一度に経費として計上することはできません。
例えば、120万円の券売機を経費で購入する場合は、券売機の耐用年数8年にわたって15万円ずつ経費として計上していきます。
なぜ分割するかというと、資産と収益の関係に矛盾が発生しないようにするためです。
また、券売機の耐用年数を過ぎた後は、減価償却を行うことはできません。
出典:国税庁 よくある税の質問 No.2100 減価償却のあらまし
勘定科目とは?
勘定科目とは、会社や個人事業主などの取引で発生する、お金の流れをわかりやすく分類するためのものです。言い換えると、お金を何に使ったのか、なぜ入金があったのかを示す「見出し」といえます。
勘定科目を使えば、帳簿を記載しても統一した内容となるため、「どのようにお金を使って、どのように入金されたのか」が誰が見てもわかるようになるのです。
例えば、家計簿をつける場合は、「光熱費」や「家賃」などの項目でお金の流れを分類するかと思います。勘定科目は「光熱費」や「家賃」などにあたるものです。
勘定科目が記載されている帳簿は、社内の人だけでなく、税理士なども見るので、正確に分類する必要があります。
券売機導入時の節税テクニック
ここでは、券売機を導入する際に使える節税テクニックを紹介します。
- 少額減価償却資産制度の活用
- お店の利益が好調な時に購入・リースする
①少額減価償却資産制度の活用
少額減価償却資産とは、青色申告をしている中小企業に限り、30万円未満の減価償却資産であれば、年度内に一括で経費計上が可能になる制度です。
通常、減価償却資産を取得する場合は、その資産の耐用年数にわたって少しずつ経費を計上していきます。
少額減価償却資産制度を活用すれば、減価償却する必要がなく、一括で経費を計上できるので、税金の支払い金額を抑えることが可能です。
新品でも中古でも適用できるため、券売機を購入して30万円未満であれば、積極的に活用していきましょう。
▶低価格な券売機については、下記の記事より探していただけます。
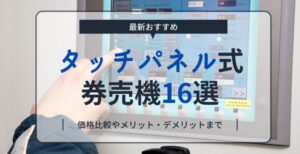
②お店の利益が好調な時に購入・リースする
お店の利益が好調であれば、払う税金は増えます。
将来的な投資と考えて券売機を購入・リースすることで、税金額を抑えることが可能です。
また、2024年7月前半を目途に新紙幣が発行されるため、券売機の入れ替え・アップデートが必要になります。
この機会に券売機を入れ替えてみてはいかがでしょうか。
▶おすすめの券売機については、下記の記事にて紹介しています。
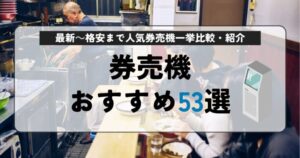
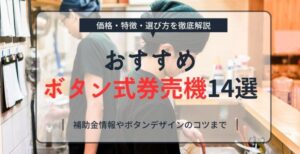
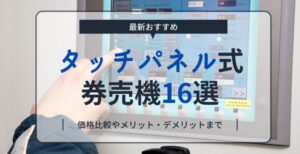
まとめ
本記事では、券売機の法定耐用年数や導入方法別の減価償却などを解説してきました。
法定耐用年数は国税庁が定めており、券売機の場合は基本的に8年※です。
ただし、以下のように導入方法によっても耐用年数は異なります。
- 購入:基本的に8年
- レンタル:特に関係なし
- リース(所有権移転):国税庁が定めた耐用年数(8年)
- リース(所有権移転外):リース契約をしている期間
減価償却の計算が面倒であれば、減価償却や財務管理を必要としないレンタルの利用も選択肢の一つです。導入の際は、導入方法や減価償却の耐用年数を確認し、自社に合った方法を選択しましょう。
券売機の関連記事一覧
-
 券売機おすすめ53選|最新~格安まで人気券売機一挙比較・紹介
券売機おすすめ53選|最新~格安まで人気券売機一挙比較・紹介 -
 最新おすすめタッチパネル式券売機16選|価格比較やデメリットまで
最新おすすめタッチパネル式券売機16選|価格比較やデメリットまで -
 券売機の法定耐用年数・勘定科目は?導入方法別の減価償却まで!
券売機の法定耐用年数・勘定科目は?導入方法別の減価償却まで! -
 1万円・5千円札対応の券売機全まとめ【高額紙幣対応機の比較】
1万円・5千円札対応の券売機全まとめ【高額紙幣対応機の比較】 -
 キャッシュレス対応券売機まとめ【クレカ・電子マネー・QR・ペイペイ】
キャッシュレス対応券売機まとめ【クレカ・電子マネー・QR・ペイペイ】 -
 券売機の新札対応方法や費用・補助金・新紙幣対応済み券売機情報まで
券売機の新札対応方法や費用・補助金・新紙幣対応済み券売機情報まで -
 券売機のメーカー・販売会社一覧|製品特徴・シェア率・上場区分を紹介
券売機のメーカー・販売会社一覧|製品特徴・シェア率・上場区分を紹介 -
 POS連動型おすすめ券売機7選【タブレット型・セルフレジ切替】
POS連動型おすすめ券売機7選【タブレット型・セルフレジ切替】 -
 券売機リース・レンタルとは?違いや魅力・料金【1日~・月額安い】
券売機リース・レンタルとは?違いや魅力・料金【1日~・月額安い】